01
人事評価について
クボテックでは、イメージ評価ではなく平等な評価を下すために、評価マニュアルに定めた人事評価表に基づき判断しております。入社後、評価マニュアルはお渡しいたしますが、一部を以下にご説明させて頂きます。
評価要素
人事評価の流れ

職務遂行能力要件、役割要件の確認
(Plan)

業務遂行
(Do)
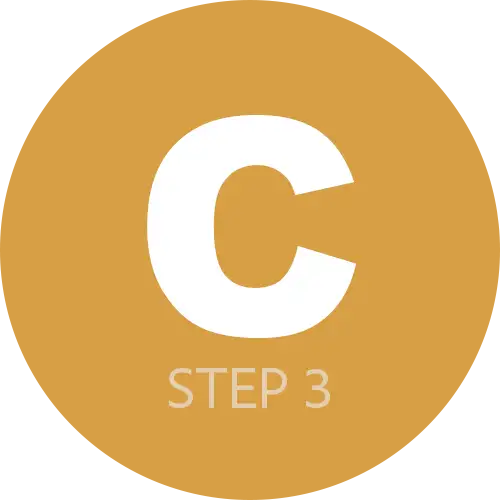
人事評価の実施
(Check)
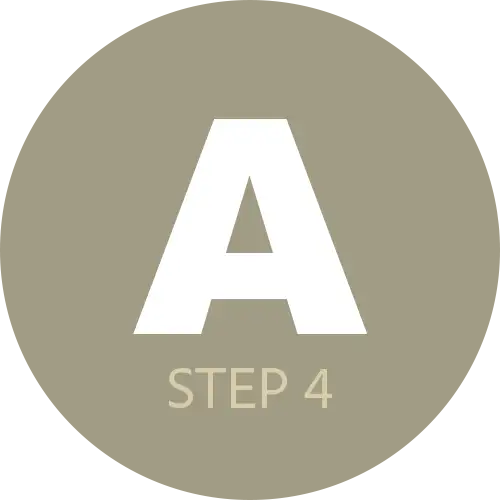
フィードバック面談
(Action)
評価ウエイト
| 行動評価 | 勤態評価 | |
|---|---|---|
| 正社員5~6等級 | 90% | 10% |
| 正社員3~4等級/ パート4等級 | 85% | 15% |
| 正社員1~2等級/ パート 1~3 等級 | 80% | 20% |
「行動評価」の評価スケール
「行動評価」は S/A/B/C/D の 5 段階のスケールとしています。
能力や役割が十分に発揮されていればより高い評価となる加点評価の方法を採っています。
| 評価スケール | 基準 |
|---|---|
| S(5 点) | 等級に対する要求を大いに満たしている上で、評価者以外から見 ても該当要件に対する働きぶりが認められると考えられる。また評 価基準によっては、一つ上の等級のレベルも満たしているようなケ ースである。 |
| A(4 点) | 等級に対する要求を満たしている上で、期待されるレベルに対し てパフォーマンスが比較的高い。また評価基準によっては、担当す る業務によって一つ上の等級のレベルも満たしているようなケース もある。 |
| B(3 点) | 等級に対する要求を概ね満たしており、日常業務において支障を 来すことなく業務を遂行できている。 |
| C(2 点) | 等級に対する要求を満たしておらず、期待されるレベルに対して パフォーマンスがやや低い。また評価基準によっては、担当する業 務によって一つ下の等級のレベルも満たしていないようなケースも ある。 |
| D(1 点) | 等級に対する要求を大きく下回る。具体的には、トラブルまたは クレームに繋がるほどのミスや問題を起こしてしまった事案があ り、また評価基準によっては、一つ下の等級のレベルも満たしてい ないようなケースである。 |
「行動評価」の算出方法
1. 各項目について5点満点で評価を実施します。
2. 各項目の平均点を算出して100点満点換算します。
3.2で出した点数に、上記評価ウエイトにて各等級で設定されたウエイトを掛け合わせます。
「勤態評価」の評価スケール
「勤態評価」は A/B/C の 3 段階のスケールとしています。ただし、規律性については「出勤率」及び「無断欠勤や無断での遅刻・早退の有無」に基づき〇×の 2 段階のスケールとしています。
「総合評価」の評価ランク
「総合評価」は S〜D の5段階としています。「総合評価」は合計点の閾値を基準とします。
なお、合計点の閾値については、相対化にあたって調整することがあります。
→評価結果が全体的に高い場合は、相対化を図るために各評価ランクの閾値の数字が全体的に高くなります。
| 評価ランク | 基準(合計点の閾値) |
|---|---|
| S | 84 点以上 |
| A | 68 点以上 84 点未満 |
| B | 52 点以上 68 点未満 |
| C | 36 点以上 52 点未満 |
| D | 36 点未満 |
02
育成について

1.業務に必要な知識と技術の研修
業務に求められるスキル向上のため、各種研修を行います。社員一人ひとりが学び、着実に成長できるよう、継続的にサポートしています。
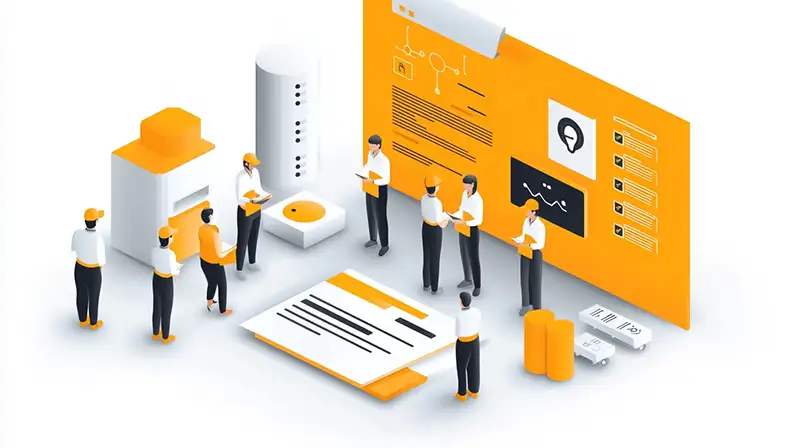
2.個人情報の保護管理教育
個人情報や特定個人情報等の安全管理を徹底するため、責任者や担当者を含めた研修を実施します。適正な取り扱いを全社で意識づけています。
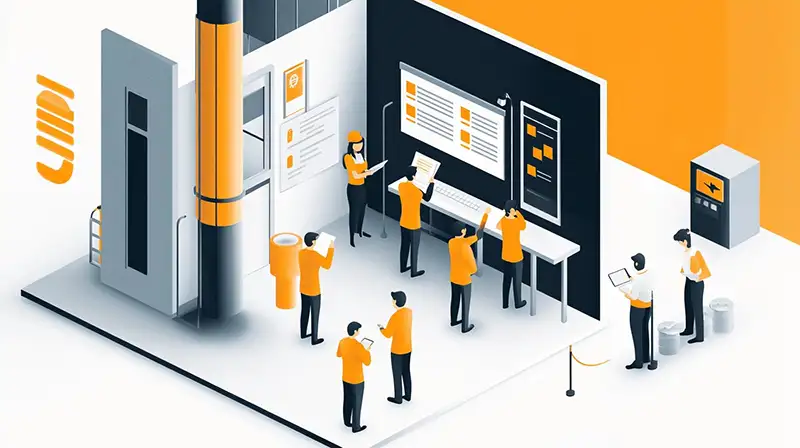
3.受講義務と時間外対応
研修受講を命じられた場合、正当な理由なく拒否できません。研修は所定時間内の実施を原則とし、時間外や休日は手当や振替で対応します。

4.1on1とフィードバック
日頃の悩みや課題を共有し、トラブルを早期に防ぐため、上長と社員が1on1を行います。フィードバックを通じて相互理解と成長を促進します。